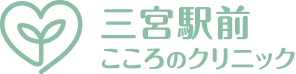「なるべく薬に頼らない治療」を基本方針としています
神戸・三宮の心療内科・精神科、三宮駅前こころのクリニックです。
こころの不調を抱えているとき、お薬による治療は選択肢の一つになります。しかし、その効果や副作用について、ご不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
当院は、患者様とじっくりお話をうかがい、生活習慣を見直すことなどを通じて、ご自身の回復力を引き出す「なるべく薬に頼らない治療」を基本方針としています。
ただ、症状が重く、休養だけではなかなか回復が難しいこともあります。つらい症状で日常生活に大きな支障が出ている場合には、一時的にお薬の力を借りることが、回復への大きな助けとなるのも事実です。
この記事では、当院がお薬による治療をどのように位置づけ、どのような考え方で安全に進めていくのか、その点をお伝えしたいと思います。
お薬による治療を行う際の当院の考え方
当院では、薬物療法はあくまで治療の選択肢の一つであり、お薬だけに頼るのではなく、ご自身の回復力を高めるための「サポート」だと考えています。そのため、お薬の処方を行う際には、いくつかの点を大切にしています。
丁寧な対話と多角的なサポート
診察での丁寧な対話や環境調整、生活指導などを治療の基本とします。その上で薬物療法を組み合わせることで、根本的な回復と再発予防を目指します。
必要最小限の処方から
お薬を始める際は、効果が期待できる最も少ない量から開始し、定期的に効果と副作用を確認しながら慎重に調整を進めます。
単剤治療を優先
原則としてお薬は1種類から始め、複数の薬を併用することはなるべく避けることで、副作用のリスクを最小限に抑えるよう努めます。
治療目標の共有
「夜眠れるようになりたい」「不安発作の頻度を減らしたい」といった具体的な治療目標を患者様と共有し、「お薬からの卒業」というゴールに向かって一緒に進んでいくことを心がけています。
自己判断での中断は避ける
お薬の量を減らしたり、やめたりする際は、離脱症状などを防ぐために計画的に行います。よくなったからと自己判断で中断せず、必ず医師にご相談ください。
お薬の種類と主な役割
※ここに記載しているのは代表的なお薬です。同じ病名でも、患者様一人ひとりの症状や体質によって最適なお薬は異なります。医師との対話を通じて、あなたに合ったお薬を一緒に探していくことが何よりも大切です。
1. 抗うつ薬(気分の落ち込み・不安に)
抗うつ薬は、脳内の神経伝達物質と呼ばれる化学物質のバランスを調整することで、心のエネルギー回復を後押しするお薬です。これらは単に気分を上げる「元気の出る薬」ではなく、脳の神経細胞間の情報伝達をスムーズにし、脳が本来持っている回復力を引き出す手助けをします。効果が安定して感じられるまでには2~4週間ほどかかることが多いですが、これはお薬が脳の働きを根本からじっくりと整えていくためです 。
抗うつ薬の開発の歴史は、より効果的で、より副作用の少ない薬を目指す歩みそのものです。初期の「三環系」のように強力ながらも作用が広範な薬から、特定の神経伝達物質に的を絞った「SSRI」、さらに複数の物質に計画的に作用する「SNRI」、そしてより複雑な仕組みで働く「NaSSA」や「S−RIM」といった新しい薬が登場してきました。この進化は、患者様一人ひとりの異なる症状や悩みに、よりきめ細かく対応するための選択肢が増えたことを意味します。どの薬が最適かは、症状の特性(例えば、不安が強いか、意欲の低下が著しいかなど)によって異なります。
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- 働き方: 脳内の神経伝達物質の中でも、気分や不安感に深く関わる「セロトニン」の働きを高めるお薬です 。神経細胞間でセロトニンが再吸収されるのを穏やかに阻害し、セロトニンがより長く、より効果的に働く時間を与えます 。
- 治療における役割: 特定の物質に的を絞って作用するため、後述する三環系抗うつ薬などと比べて副作用が少なく、多くのうつ病や不安症の治療で最初に選択されることが多い「第一選択薬」です 。
- 代表的なお薬:
- セルトラリン(ジェイゾロフト®): 少ない量から始められ、徐々に調整しやすいのが特徴です。セロトニンだけでなく、喜びや意欲に関わる脳の部位でドパミンの働きも高める可能性が示唆されています 。
- エスシタロプラム(レクサプロ®): 効果と副作用のバランスが良く、忍容性が高いとされるお薬の一つです。うつ病だけでなく、パニック症など様々な不安症状に対しても有効性が示されています 。
- パロキセチン(パキシル®): 効果が力強い印象があり、特に社交不安症に対して高い効果が報告されています。一方で、他のSSRIに比べて副作用や中断時の離脱症状が出やすい傾向があるため、慎重な調整が必要です 。
- フルボキサミン(ルボックス®、デプロメール®): シグマ-1受容体という特殊な部位にも作用し、精神病症状を伴ううつ病や認知機能への良い影響も期待されています 。
- 知っておきたいこと: 飲み始めの1~2週間に吐き気などの胃腸症状が出ることがありますが、多くは体が慣れるにつれて自然に軽快します 。急に服用を中止すると、めまいやふらつきなどの離脱症状が起こることがあるため、減量や中止は必ず医師と相談しながら計画的に行います 。
SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
- 働き方: セロトニンに加えて、意欲や集中力に関わる「ノルアドレナリン」という神経伝達物質の働きも同時に高める「デュアルアクション(二重の作用)」を持つお薬です 。
- 治療における役割: 気分の落ち込みだけでなく、「やる気が出ない」「何もする気になれない」といった意欲の低下が強い場合や、原因のはっきりしない身体の痛み(慢性疼痛)を伴う場合に特に有効な選択肢となります 。
- 代表的なお薬:
- デュロキセチン(サインバルタ®): セロトニンとノルアドレナリンの両方に強力に作用します。意欲に関わる脳の前頭前野でドパミンの働きも高めることが分かっており、身体の痛みを和らげる効果も高いのが特徴です 。
- ベンラファキシン(イフェクサー®SR): 服用する量によって作用の仕方が変わるユニークなお薬です。少ない量ではSSRIのようにセロトニンに主に作用し、量を増やしていくとノルアドレナリンへの作用が強まり、意欲を高める効果がより期待できます 。
- ミルナシプラン(トレドミン®): 比較的ノルアドレナリンへの作用が優位で、全体的な作用は穏やかです。副作用に敏感な方やご高齢の方にも使いやすい選択肢とされています 。
- 知っておきたいこと: ノルアドレナリンに作用するため、血圧が少し上がることがあります。医師が定期的に確認しますのでご安心ください。SSRIと同様、自己判断での中断は避ける必要があります。
NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
- 働き方: SSRIやSNRIとは全く異なる仕組みで作用します。神経細胞にある「ブレーキ」の役割を持つ受容体をブロックすることで、セロトニンとノルアドレナリンの放出を直接的に促進させます 。
- 治療における役割: 「夜、全く眠れない」「食欲がなくて体重が減ってしまった」など、不眠や食欲不振が特に深刻な場合に非常に有効です 。多くの場合、気分の改善よりも先に睡眠や食欲への効果が1~2週間で現れるため、つらい身体症状を早期に和らげる助けになります 。
- 代表的なお薬:
- ミルタザピン(リフレックス®、レメロン®): このタイプで唯一のお薬です。効果の発現が比較的早いことで知られています 。
- 知っておきたいこと: 最も特徴的な副作用は、強い眠気と食欲の増加です。このため、通常は就寝前に服用します。この眠気を利用して不眠を改善できる一方、日中まで眠気が残ることもあります。食欲増進から体重が増加することもあるため、注意が必要ですが、食事がとれずに困っている方にとっては、この作用が治療的なメリットになります 。
S-RIM(セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬)
- 働き方: SSRIのようにセロトニンの量を増やすだけでなく、複数のセロトニン受容体の働きを直接調整(モジュレート)するという、多面的な作用を持つ新しいタイプのお薬です 。セロトニンというメッセージの「量」を増やすだけでなく、そのメッセージを脳がより効果的に受け取れるように「受信感度」を調整するイメージです。
- 治療における役割: この複雑な作用により、うつ病に伴う「集中できない」「考えがまとまらない」といった認知機能の低下を改善する効果が期待されています 。また、性機能への影響や、中断時の離脱症状が他の抗うつ薬に比べて少ないという利点もあります 。
- 代表的なお薬:
- ボルチオキセチン(トリンテリックス®): 気分の症状だけでなく、生活の質に大きく影響する認知機能にもアプローチできるのが大きな特徴です 。
- 知っておきたいこと: 飲み始めに吐き気が出やすいことが報告されていますが、食事と一緒に服用することで軽減できる場合があります 。体内でゆっくりと作用し、長く留まるため、減薬・中止の際に離脱症状が起こりにくいとされています 。
三環系抗うつ薬
- 働き方: 最も歴史の古い抗うつ薬の一つで、セロトニンとノルアドレナリンの働きを強力に高めます 。その効果は非常に高いですが、作用が新しい薬ほど「選択的」ではないのが特徴です。
- 治療における役割: 副作用が出やすいため第一選択薬となることは少ないですが、他の新しい薬で十分な効果が得られなかった重度のうつ病に対して、今なお重要な治療選択肢です 。
- 代表的なお薬:
- クロミプラミン(アナフラニール®): 特にセロトニンへの作用が強く、うつ病だけでなく強迫症(OCD)の治療にも高い効果を発揮します 。
- アミトリプチリン(トリプタノール®): 強力な抗うつ効果に加え、慢性的な痛みや片頭痛の予防にも広く用いられています 。
- 知っておきたいこと: 三環系抗うつ薬は、目的の神経伝達物質以外にも、ヒスタミンやムスカリンといった様々な受容体に作用します 。このため、眠気、口の渇き、便秘、立ちくらみといった副作用が新しい薬に比べて出やすい傾向があります 。効果が高い分、より慎重な管理が必要なお薬です。
参考:うつ病について
2. 睡眠薬(眠りの問題に)
「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」といった不眠のタイプに合わせて、自然な眠りの手助けをします。睡眠薬は、その働き方によって大きく2つのタイプに分けることができます 。
- 脳の活動を穏やかにするタイプ: 脳の興奮を鎮める神経伝達物質GABAの働きを強めることで、眠りを誘います 。
- 非ベンゾジアゼピン系(Z薬): 睡眠に特化した受容体(ω1)に選択的に作用するため、従来のベンゾジアゼピン系に比べて、ふらつきの原因となる筋弛緩作用が少なく、依存のリスクも低いとされています 。ゾルピデム(マイスリー®)などがこれにあたります。
- ベンゾジアゼピン系: 催眠作用のほかに抗不安作用や筋弛緩作用も併せ持ちます 。作用時間の長さ(超短時間型~長時間型)の種類が豊富で、不眠のパターンに合わせて細かく使い分けることができます 。
- 自然な眠りを後押しするタイプ: 体が本来持っている睡眠のリズムを利用したり、覚醒のシグナルを抑えたりすることで、より自然に近い眠りへと導きます 。
- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を整える睡眠ホルモン「メラトニン」の受容体に作用し、睡眠のリズムを整えます。特に寝つく時間が不規則な方に有効です 。
- オレキシン受容体拮抗薬: 脳を「起きろ」と覚醒させる物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、脳を覚醒状態から睡眠状態へと切り替える手助けをします。依存性が極めて低い新しいタイプのお薬です 。
お薬の選択は、寝つきが悪いのか(入眠障害)、途中で目が覚めるのか(中途覚醒)など、不眠のタイプによって異なります 。例えば、入眠障害には効果の立ち上がりが早い短時間作用型を、中途覚醒には効果が長く続く中時間作用型やオレキシン受容体拮抗薬を用いるなど、きめ細かく調整します 。お薬だけに頼るのではなく、まずは睡眠環境を整えることと並行して行います。
参考:睡眠障害(睡眠症)について
3. 抗不安薬(急な不安・緊張のピークに)
どうしても我慢できない強い不安や、それに伴う動悸・ふるえといった身体症状を一時的に和らげます。主にベンゾジアゼピン系(アルプラゾラムなど)のお薬が用いられます 。
この系統のお薬は、脳の興奮を鎮めるGABAの働きを強めることで、速やかに不安を軽減する効果があります 。しかし、その速やかで確実な効果が、「不安になったら薬を飲むと楽になる」という強い心理的な結びつきを生みやすく、精神的な依存につながる可能性があります 。また、長期間使用することで体が薬のある状態に慣れてしまい、薬がなくなると離脱症状(不安の再燃、不眠など)が現れる身体的依存を形成することもあります 。
このため、当院ではベンゾジアゼピン系抗不安薬の使用は、あくまで一時的な「頓服(とんぷく:つらい時だけ飲む)」を原則とし 、漫然と長期間使用することがないよう、必要最小限の期間と量にとどめることを徹底しています。
参考:パニック症(パニック障害)について
参考:社交不安障害について
4. 抗精神病薬(思考や知覚の不調・気分の波に)
妄想や幻聴といった症状を軽減したり、激しいいらだちを鎮めたり、双極症の気分の波を安定させたりする役割があります。統合失調症の治療の中心となるお薬ですが、うつ病の治療で補助的に使われることもあります。脳内のドパミンという神経伝達物質の過剰な働きを抑えることが主な作用です 。
抗精神病薬は、開発された年代や作用機序によって大きく二つに分けられます。
- 第一世代(定型)抗精神病薬: ドパミンを強力にブロックすることで、幻覚や妄想といった陽性症状に高い効果を発揮します。しかし、運動機能に関わる副作用(手足のふるえや体のこわばりなど:錐体外路症状)が出やすいという特徴があります 。 代表的なお薬には、ハロペリドール(セレネース®)があります。
- 第二世代(非定型)抗精神病薬: ドパミンだけでなくセロトニンにも作用することで、第一世代薬に比べて錐体外路症状のリスクが低減されています。また、意欲の低下や感情の平板化といった陰性症状にも効果が期待できます 。その一方で、薬の種類によっては体重増加や血糖値の上昇といった代謝系の副作用に注意が必要です 。 代表的なお薬には、オランザピン(ジプレキサ®)、リスペリドン(リスパダール®)、クエチアピン(セロクエル®)、アリピプラゾール(エビリファイ®)、ブレクスピプラゾール(レキサルティ®)、ルラシドン(ラツーダ®)などがあります。
どちらの薬が良い・悪いということではなく、それぞれの薬にメリットとデメリットが存在します。例えば、代謝系の疾患をお持ちの方には第二世代薬を慎重に選び、運動系の副作用に敏感な方には第一世代薬を避けるなど、患者様一人ひとりの状態に合わせて、最も利益が大きく、リスクが少ないと考えられる薬を選択します。このため、使用中は体重や血糖値への影響、副作用がないかなどを定期的なモニタリングで安全を確認しながら治療を進めます。
参考:統合失調症について
5. 気分安定薬(気分の波の再発予防に)
主に双極症(躁うつ病)の患者様に対して、気分の上がりすぎ(躁状態)と落ち込みすぎ(うつ状態)の波を穏やかにし、長期的に安定させるために用います 。再発を予防することが治療の最も重要な目標となります。
代表的なお薬には、炭酸リチウム(リーマス®)、バルプロ酸(デパケン®)、ラモトリギン(ラミクタール®)などがあります 。これらのお薬は、躁状態とうつ状態のどちらに、より効果が期待できるかといった特性が少しずつ異なります 。
特に炭酸リチウムなど一部のお薬は、効果と安全性のバランスを慎重に見極める必要があります。そのため、医師の指示通りに用法・用量を厳密に守っていただくことが非常に重要です。自己判断でお薬の量を変えたり中断したりせず、気になる体調の変化があれば速やかにご相談ください。
患者様一人ひとりに合わせて、最も安全で効果的な治療法を一緒に考えてまいります。妊娠の計画がある場合は、胎児への影響を考慮する必要があるため、必ず事前にご相談ください。
参考:双極性障害(躁うつ病)について
その他のお薬について
その他、ADHD(注意欠如・多動症)の症状(不注意・多動性)を改善するお薬(中枢神経刺激薬のメチルフェニデート(コンサータ®)や非刺激薬のアトモキセチン(ストラテラ®)など )、認知症の進行を緩やかにするお薬(コリンエステラーゼ阻害薬のドネペジル(アリセプト®)や
NMDA受容体拮抗薬のメマンチン(メマリー®)など )、アルコール依存症の治療で断酒を補助するお薬(飲酒欲求を抑えるアカンプロサートや、飲酒時に不快な症状を起こさせるシアナミドなど )など、目的に応じた様々なお薬があります。いずれも、その必要性を慎重に判断し、安全を確認しながら使用します。
参考:注意欠如・多動症(ADHD)について
参考:認知症について
準備中
参考:アルコール依存症について
準備中
よくあるご質問
Q. 薬を使わずに治療することはできますか?
はい、それが当院の基本方針です。まずは診察でじっくりとお話をうかがい、生活指導や環境調整など、お薬を使わない治療法から検討します。薬物療法は、患者様とご相談し、必要性が高いと判断された場合にのみ、選択肢としてご提案します。
Q. どのくらいの期間、薬を続けますか?
症状や薬の種類によって異なりますが、最終的には「お薬からの卒業」を目指します。症状が十分に改善した後も、再発を防ぐために一定期間の服用を続け、その後、医師の判断のもとで計画的に減量・中止していきます。
まとめ:お薬は回復までの「杖」です
私たちは、お薬を「つらい時期を乗り越えるための杖」のようなものだと考えています。
杖を使いながら心と体を休ませ、医師との対話を通じてご自身の状態への理解を深め、歩き方を練習する。そして、ご自身の力が回復してきたら、少しずつ杖に頼るのをやめて、いずれは杖なしでしっかりと歩いていけるようになる。
それが当院の目指す治療のゴールです。お薬に関する不安や疑問は、どんな小さなことでもご相談ください。あなたに合った回復への道を一緒に探していきましょう。