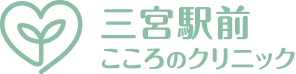休職
仕事のストレスや環境の変化で心身が疲弊し、「もう限界かもしれない」「少し休みたい」と感じていませんか?そのような時、選択肢の一つとなるのが「休職」です。
しかし、休職という言葉は知っていても、「具体的にどうすればいいの?」「お金のことは?」「会社には何て言えば?」など、分からないことが多くて不安に感じてしまう方も少なくありません。
この記事では、休職にまつわる様々な疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説していきます。一人で抱え込まず、正しい知識を得て、ご自身の心と体を守るための一歩を踏出しましょう。
-
「休職」とは、そもそも何ですか?
-
休職とは、自己都合の理由(病気やケガなど)によって、労働者が会社との労働契約を維持したまま、長期間仕事を休むことを指す制度です。法律で定められた制度ではなく、会社の就業規則に基づいて運用されるのが一般的です。
退職とは異なり、会社に籍を置いたまま治療や療養に専念できるのが大きな特徴です。まずはご自身の会社の就業規則で、休職に関する規定を確認することが大切です。
-
どんな状態になったら休職を考えるべきですか?
-
もし以下のような心身のサインが続いているなら、休職を検討するタイミングかもしれません。
- 朝、どうしても起き上がれない、会社に行く気力がわかない
- 仕事中に涙が止まらなくなったり、強い不安感に襲われたりする
- これまで楽しめていた趣味に全く興味がなくなった
- 食欲がない、または過食してしまう日が続く
- 不眠(寝付けない、夜中に何度も目が覚める、早朝に目が覚める)が続く
- 頭痛、めまい、腹痛、動悸など、原因の分からない身体の調がある
- 仕事での単純なミスが増え、集中力や判断力が著しく低下した
これらの症状は、うつ病や適応障害などのサインである可能性も考えられます。無理を続けると症状が悪化してしまう恐れがあるため、「おかしいな」と感じたら、お早めに医療機関へご相談ください。
-
休職するには、まず何をすればいいですか?
-
休職までの一般的な流れは以下の通りです。
- 医療機関の受診
まずは心療内科や精神科を受診し、医師の診察を受けます。現在の症状や仕事の状況などを詳しくお話しください。 - 診断書の発行
診察の結果、療養が必要だと医師が判断した場合、「休職が必要な旨を記載した診断書」を発行します。 - 会社への申し出と診断書の提出
直属の上司や人事担当者に、医師の診断結果を伝えて休職を希望する旨を申し出ます。その際に診断書を提出します。医師の診断書は、あなたの状態を客観的に伝えるための重要な資料ですが、最終的な休職の判断は会社の就業規則に基づいて行われます。 - 会社との手続き
会社の担当者と、休職期間、休職中の連絡方法、社会保険の手続きなどについて確認し、必要な書類を提出します。
三宮駅前こころのクリニックでは、患者様の状況を丁寧にお伺いし、休職が必要かどうかを一緒に考えさせていただきます。診断書の発行も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 医療機関の受診
-
診断書には何が書かれていますか?
-
A. 診断書は、あなたの健康状態を会社に証明するための公的な書類です。一般的には以下の内容が記載されます。
- 病名(診断名):うつ病、適応障害など
- 症状:上記で挙げたような具体的な心身の状態
- 必要な療養期間:「〇ヶ月の自宅療養を要する」といった形で記載されます
- 療養中に避けるべきこと:業務内容の制限などに関する医師の意見
会社はこの診断書に書かれた医学的な見解を尊重し、休職の手続きを進めることになります。
-
休職中、お給料がもらえないのが心配です…
-
休職中は会社からの給与が支払われないことがほとんどですが、生活を支えるための公的な制度として「傷病手当金」があります。
傷病手当金は、ご自身が加入している健康保険から支給されるもので、以下の4つの条件をすべて満たす場合に受け取ることができます。
- 業務外の病気やケガのための療養であること(労災は対象外)
- 働くことができない状態であること(医師の証明が必要)
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
- 休んだ期間について、会社から給与の支払いがないこと
支給額は、大まかには「月給の約3分の2」が目安となり、支給開始日から通算で1年6ヶ月分受け取ることができます。申請には医師の意見書や会社からの証明が必要となりますので、ご不明な点は当院または会社の担当者にご相談ください。
こちらの記事もご参照ください。
-
休職中は、どのように過ごせばいいですか?
-
焦らず、段階的に心身を回復させていくことが大切です。一般的に、以下のような3つのステップで過ごすのが良いとされています。
第1段階:休息期(はじめの1〜3ヶ月) とにかく心と体を休ませることに専念する時期です。「何かしないと」と焦る必要はありません。十分な睡眠をとり、栄養のある食事を心がけ、リラックスして過ごしましょう。
第2段階:リハビリ期(回復してきたら) 気力や体力が少しずつ戻ってきたら、生活リズムを整え、軽い活動を始める時期です。朝に散歩をする、図書館に行く、簡単な家事をするなど、少しずつ活動範囲を広げていきましょう。
第3段階:復職準備期(復職が見えてきたら) 会社の勤務時間に合わせて生活リズムを整え、復職に向けた準備をする時期です。通勤の練習をしたり、仕事に関連する本を読んだりして、心と体を慣らしていきます。
-
復職は、どのように進めればいいですか?
-
A. 復職は、ご自身の判断だけで進めるのではなく、「ご本人」「会社」「主治医」の三者が連携して慎重に進めることが重要です。
まず、ご自身で「復職できるかもしれない」と感じたら、主治医に相談してください。医師が回復状態を判断し、復職可能と判断すれば、その旨を記載した診断書(意見書)を作成します。
その診断書を会社に提出し、会社の担当者や産業医(※)と面談を行います。面談では、復職後の働き方(時短勤務や業務内容の調整など)について具体的に話し合います。こうした復職へのプロセスは、国が示すガイドラインに沿って進められるのが一般的です。
(出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」)
焦りは禁物です。再発を防ぐためにも、主治医とよく相談しながら、無理のないペースで復職を目指しましょう。
※産業医:一定規模以上の事業場に選任が義務付けられている、労働者の健康管理を行う医師。
ご自身の心と体を守るために
休職は、決して特別なことではありません。それは、あなたがこれからも健康に働き続けるために必要な「治療期間」であり、「次へ進むための準備期間」です。
三宮駅前こころのクリニックでは、働く方々のメンタルヘルスをサポートしております。「もしかして…」と感じたら、一人で悩まず、どうぞお気軽に当院へご相談ください。