HSP(Highly Sensitive Person)とは
HSP(Highly Sensitive Person)とは、生まれつき感覚的な刺激に敏感で、周囲の環境や人の感情から強い影響を受けやすい「気質」を持つ方を指す言葉です。
周囲の雰囲気のわずかな変化や、相手の表情の揺れにすぐに気づき、深く共感するあまり、ご自身の心と身体が疲弊してしまう——。もし、そのようなことで「生きづらさ」を感じているなら、それはあなたが持つ繊細で豊かな感受性ゆえかもしれません。
この概念は1996年にアメリカの心理学者エレイン・N・アーロン氏によって提唱されたものであり、医学的な病名ではありません。あくまで、その人が生まれ持った「気質」の一つです。そのため、HSP自体を「治療」するという考え方はせず、その気質と上手に付き合い、日々の負担を軽くしていく工夫を見つけることが何よりも大切になります。
HSPの気質を持つ方は、全人口の約15〜20%、およそ「5人に1人」いると言われており、決して珍しい存在ではありません。
HSPの主な4つの特徴(DOES)
アーロン氏は、HSPに共通する特徴を「DOES(ダズ)」という4つの頭文字で説明しています。
D:深く処理する(Depth of processing)
物事を多角的かつ深く掘り下げて考えます。表面的な情報だけでなく、その裏にある意味や関連性までじっくり吟味するため、結論を出すのに時間がかかる傾向があります。
O:過剰に刺激を受けやすい(Overstimulation)
人混みの中にいたり、大きな音や強い光を感じたり、複数の人が同時に話す会議に参加したりすると、多くの刺激を一度に受け取ってしまい、神経系が過剰に興奮して心身のエネルギーを消耗しやすく、ひどく疲れてしまいます。
E:全体的な感情の反応が強く、特に共感力が高い(Emotional reactivity & high Empathy)
他人の感情をまるで自分のことのように感じ取ります。相手の喜びや悲しみに深く共感するため、感情移入しすぎて疲れてしまうことがあります。ポジティブ・ネガティブ両方の感情に強く反応します。
S:ささいな刺激を察知する(Sensing the subtle)
他の人が気づかないような、音、匂い、光、人の表情や声色のトーンといった、ごく微細な違いや変化によく気づきます。
HSPのセルフチェックリスト
以下の項目に当てはまるものが多いほど、HSPの傾向があるかもしれません。 (※あくまで簡易的な目安であり、医学的な診断ではありません)
- 他人の気分に大きく左右されてしまう。
- 騒がしい環境にいると、不快ですぐにでも離れたくなる。
- 一度に多くのことを頼まれると、混乱してしまう。
- 大きな音や強い光、特定の匂いがひどく苦手だ。
- 芸術や音楽に深く心を動かされやすい。
- 暴力的な映画やニュースを見ると、何日も気分が落ち込む。
- 他人の些細な言動が気になり、後から何度も考えてしまう。
- 忙しい日々が続くと、一人で静かに過ごせる場所に引きこもりたくなる。
- 痛みやカフェイン、薬の影響を人より強く受けやすい気がする。
- 子どもの頃、親や教師から「繊細だ」「内気だ」と言われたことがある。
HSPの原因
HSPは後天的なものではなく、生まれ持った脳の神経システムの違いによるものと考えられています。脳の中でも、特に危険を察知する扁桃体や、共感や注意を司る島皮質といった部位が、生まれつき強く活動しやすい傾向があるとされています。
つまり、性格や育て方の問題ではなく、脳機能の特性なのです。ご自身を「弱い」「考えすぎだ」と責める必要はまったくありません。
HSPの気質との付き合い方と当院のサポート
HSPは病気ではないため、「治療」の対象にはなりません。しかし、その繊細さゆえに知らず知らずのうちにストレスが積み重なり、心がSOSを発した結果として、不安障害やうつ病、適応障害、不眠症といった状態に至ることが少なくありません。これらの状態には、医学的なサポートが有効です。
目標は「敏感さをなくす」ことではなく、「生きづらさを軽くする」ことです。そのために、ご自身でできる工夫と、医療機関ができるサポートがあります。
ご自身でできる工夫(セルフケア)
- 刺激の量を調整する:一人の時間や静かな環境を意識的に確保する。例えば、ノイズキャンセリングイヤホンを使ったり、アイマスクで光を遮ったりするのも有効です。
- 物理的な境界線を引く:頼まれごとを断る練習をする。「少し考えさせてください」など、ワンクッション置く言葉を用意しておきましょう。
- 休息を予定に入れる:予定と予定の間に何もせずリラックスする時間を設ける。
- 心身の土台を整える:質の良い睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、自律神経を安定させ、刺激への耐性を高めます。
受診をご検討いただく目安
セルフケアを試みても、以下のような状態が続く場合は、お一人で抱え込まずに専門機関へご相談ください。
- 不安や気分の落ち込み、不眠が続き、日常生活に支障が出ている。
- 「自分はダメだ」という自己否定感が強く、物事を楽しない。
- 原因のわからない頭痛、腹痛、めまい、慢性的な疲労感が続いている。
- 仕事や学校に行くのが、身体的・精神的につらくてたまらない。
三宮駅前こころのクリニックでのサポート
当院では、HSPの気質を持つ方の「生きづらさ」を軽減し、安心して自分らしく過ごせるためのサポートを行っています。
まず、丁寧な問診を通じて、ご本人が感じている困難さや心身の状態を整理します。その上で、HSPの気質について正しく理解していただくための心理教育や、刺激をコントロールするための具体的な生活上のアドバイスを行います。
もし、不眠、不安、抑ううといった症状が生活の質を大きく下げている場合は、ご本人と相談の上で、それらの症状を和らげるための薬物療法を慎重に検討します。また、必要に応じて休職や職場環境の調整に関する診断書を作成することも可能です。
よくあるご質問(FAQ)
Q. HSPは薬で治せますか?
A. HSPは生まれ持った気質ですので、薬で変えることはできません。しかし、併発している不眠、不安、抑うつといった症状に対しては、薬物療法が心身の負担を和らげる上で非常に有効な場合があります。
Q. 診断書はもらえますか?
A. HSPという理由だけでは診断書の発行はできません。しかし、HSPの気質が背景となり、うつ病や適応障害といった医学的な診断基準を満たす状態であれば、診断書の発行は可能です。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください
「こんなことで相談していいのかな?」と感じる必要は全くありません。その「生きづらさ」は、あなたが持つ素晴らしい個性の一部でもあります。ご自身の繊細な気質と上手に付き合っていく方法を、私たちと一緒に考えていきませんか。
監修:宇治田直也(三宮駅前こころのクリニック 院長)
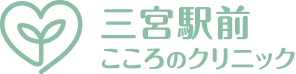

三宮駅前こころのクリニック様内観④-2-300x225.jpg)